参加者による個人レポート
山本真紀 wrote:
朗読嫌いの私が、何故、このような企画をしたかというと、ひとえに、ファン心理の暴走した結果である。国語の教師でありながら、短歌も俳句もそう好きではなかった私に、初めて「いいなあ」と思わせて下さった荻原裕幸さんと、出会ってみたい。お話ししてみたい。私たちが朗読するといえば、もしかして来ていただけるんじゃないか。そんな邪心にみちた動機で、はじまった、この企画。一番の被害者は、役者Dだったかも知れない。
「やっぱ、男歌は、男声で読まないとね〜」
「三十代、サラリーマン、男性。日常に疲れ気味!? イメージ近い近い!」
てな感じで、Dをむりやり企画に巻き込んでしまった。すべての子音の発音がおかしいというハンディキャップを背負ったDが、どのような艱難辛苦の果てにステージを踏んだかは、本人が語ると思うので、ここでは言及しない。
稽古をはじめて最初の頃は、たった二首の短歌を、何時間も繰り返し唱えることですぎていった。
「宥されて」
「もう一度」
「宥されて」
「ユが弱い」
「宥されて」
「ルが消えた」
「宥されて」
「やけくそに怒鳴らない!」
唱えるほうも苦痛だが、じっと耳を澄まして聴いている演出Nのほうが、もっとつらい作業だっただろう。けれども、演出はあきらめなかった。ウォーミングアップを除いて一日約5時間の稽古を、ただひたすら、私の微妙な声のトーンや発音の違いに熱意をかたむけるという、拷問とも思える時間を共にたえぬいてくれた彼女に、心からの感謝を捧げる。
私の発声の特徴は、但馬弁特有のヨーデルのような抑揚の激しさと、子音が弱く母音が強調される発音、そして、イ段・ウ段が苦手なことである。いつまで経っても明瞭に「宥されて」が発音できない私に、演出は、それこそ、思いつく限り、ありとあらゆる手法を試した。一音ずつ区切って、叫ぶ。百人一首かるたの読み手のように、詠じる。観世流謡の発声を用いて、朗誦する。少しずつ、滑舌がよくなってきたな、と自分でも感じはじめたのが、7月の半ばだった。すでに、稽古開始から2か月が過ぎていた。
演出Nが、「立体読み」を提唱したのは、私とDという、やっかいな朗読者に対する苦肉の策ではなかったのか、という疑いは捨てきれない。もちろん、荻原裕幸さんの短歌の、わざと読みづらくしているのかと思われるほど、日本語の発音に無頓着な音の並びに対抗する意味もあっただろう。
宥されてけふも翡翠に生きてゐる気がする何が宥してゐるのか
五七五七七に区切ると、各句の最初の音は、「ゆ」「きょ」「い」「き」「ゆ」となる。この中で、強勢で発音できるのは、「きょ」だけ、後はどうしても強く発音できない。各句の前に間をおいただけでは、句頭の音自体の弱さをカバーしきれない。子音を強くする、音量を上げる、高いトーンで発音する、ゆっくり読む、いろいろ試したが、駄目だった。とても音読に向いた歌とは思えず、途方に暮れた。
たとえば、
「地球儀」
「不思議」
などの単語を、歌の中で主眼となる重要な語句として用いるとする。視覚的に文字情報によって黙読された場合、これらの語句は、読者の頭の中で文意が整理されるなかで、アクセントつきで受け止められるだろう。しかし、音読によってアクセントをつけようとすると、やっかいである。
「チ球儀」
「フ思議」
と、母音無声化現象によって、最初の音が消えてしまい、どうしても強くは発音できない。また、イ段・ウ段や、ナ行・ヤ行・ラ行などのやわらかい子音ではじまる語も、同様に、最初から強勢で読むことは不可能である。
こんな語句が、キイワードになっていたり、五七五七七の句頭におかれていたりするのだ。それも、しょっちゅう。断言しよう。荻原裕幸の短歌は、朗読には向いていない。
朗読が、「ライブ」である、という意見には、反対だ。たしかに、朗読の会場によっては、客の顔が見えるから反応を窺いつつ演ることもできる。しかし、ライブだからといって、練習せずにいきなりぶっつけ本番、というやり方には反対だ。ひとさまにお聴かせするのだから、またお金を頂く以上、百本ノックくらいはすべきだ。
つらいつらい朗読の稽古を通して、私が得たものは、実にかろやかにまわる口と、いきいきとしたダイナミックな表現ができる声。芝居の公演を一本やるより、得るものは大きかったのではないか、とさえ思う。
稽古半ばから、実は、声に出して読むことがたのしかった。読んでいて、笑い出したいような気分で、テクストに向かい合っていた。今や、私は朗読が嫌いではない。むしろ、大好きと言っていいくらいだ。休職中の現在は、人前で朗読する機会はそうないのだが、復職してから授業で朗読するのが、楽しみだ。思う存分、本気で、たのしく読んでやろう。そして、生徒たちの目がかがやくのが見たい。
演劇人も、素人さんも、朗読を一度お試しあれ! ただし、本気でね。百本ノックは必須だよ。
今井大 wrote:
生まれてから数十年、日本語以外を生活に使ったことはありません。にもかかわらず、今回の「対戦相手」は日本語そのものでした。
もう少し正確に記すと「自分の中の日本語」と「皆が使う日本語」との差を認識させられた場でした。
日常・非日常を問わず言葉を発するのは、自分の意思表示が唯一の目的です。それが世間話であっても、会議やプレゼンテーションであっても、あるいはお芝居の中の役者であっても、です。
これらは全て「自分の中の日本語」を使ってきました。
自分の意思を伝えるには自分の言葉でなければ伝わらないからです。
ところが、今回のお題「聞き手に正確に伝える」となると、ココまで違うものかとのた打ち回る結果になりました。
- 文章を先読みしてまず印象を掴む(要は大雑把にしか捉えない)
- 詳しい情報は必要な時だけ良く見る(必要と思わなければ見ていない)
という自分の中の認知構造のため、誤読が頻発しました。
加えて、あまり口の回らない私が意思表示のためだけに育ててきた発声上の悪癖も、意思を排した表現には大きな障害となりました。
言葉は、元々意思の中から湧き上がってきて文字なり音声になったものであり、おそらく一人ひとりが独自の「日本語」を持っていて、それが個性の一部として発露していると考えています。
そういった個人の差異を乗り越えて前提無く不特定の聞き手に予断無く伝えるには共通の言語に基づく必要がある、そのためには意思伝達としての言語ではなく、情報伝達としての言語精査が不可欠であることを実感したのが今回の朗読会でした。
山本奈穂子 wrote:
「朗読」の定義は人それぞれだと思いますが、私は「テクストを声によって正確に、かつ聴衆に心地よい形で伝えること」だと考えています。
この「正確さ」というのが結構くせもので、文字通り読めば正確なのか?と言われると、そうではありません。力量ある演出家や役者の手にかかれば、作者の思いもよらぬ解釈を付加することは容易ですし、あるいは読解不足でうっかりどうでもいい単語を強調してしまったりすることもあります(結構そういう例を見たことがあります)。
今回、そういった独自の解釈を排除する手段として、センテンスの内部構造のみを忠実に声で表現する「立体読み」を導入することにしました。
「立体読み」をすると、修飾語が弱められる一方で、主語・述語といった文の根幹が浮き上がります。さらに、当日のアフタートークでは時間がないため端折りましたが、文節内においても、名詞等の自立語は強く、助詞等の付属語は弱くなります。
こうやって書くと簡単そうに見えるかもしれませんが、実際には実演するには、文節単位どころか、一音単位で、母音と子音の検証をする必要がありました。ばらばらの音のつらなりが単語になり、文節になり、センテンスに組み上がるまで──、執拗とも言える私のチェックに耐えたMとDには、心から賞賛を送りたいと思います。
さて、ここで、荻原短歌を朗読する上で困った点を一つ。
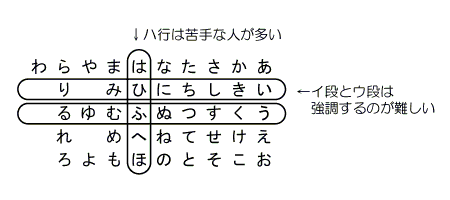
上の図にあるように、ハ行・イ段・ウ段は一般的に苦手だったり弱かったりする人が多いのですが(もちろん個人差はありますので例外もありますが)、荻原さんの短歌では、その強調しづらい音で始まる単語がキーワードであるパターンが頻出するのです……。
例として、連作『ポケットエンジェル』の最初の三首をあげます。
三十代のみどり静かにみちわたり微かにぼくがゐることを識る
目覚ましがはりのソフトは二十二世紀のLAの空を奏でる雲雀
睡蓮をも革命できずにゐるうちにみづいろ系の朝がまた来た
特に一首目の「──みどり──みちわたり──ゐる──識る」は典型的な例かもしれません。また、二首目と三首目も、センテンス内で最も強者である文節は「雲雀」と「来た」です。
役者にとって非常にいい訓練になったのは確かですが、荻原さんの好みが「みづいろ」や「みどり」じゃなくて「あお」とか「こん」だったら良かったのに、と思ったのも事実です(笑)
普段私が演出をやっている演劇では、独自解釈をいかに加えるかが問題となってきます。対象である戯曲も、役者や演出家が自分らしさを足せるように、遊びの部分を考慮して書いてあることが多いです。(全てを台詞で説明している戯曲もありますが、非常に演じにくいし、演出しにくいものです)
ですから、今回の「文学作品として既に成立している」短歌を「朗読」するという経験は非常に珍しいものでした。
一番の驚きは、同じ作者の作品を同じ演出家のもとで論理的に立体読みしているはずなのに、役者の個性はそのまま残っている、という点でしょう。単独ではなく二人で朗読した連作『ポケットエンジェル』で、それは顕著でした。どうやっても反発してしまって、お互いに歩み寄ることも出来ないのです。「演技なら似せられるけど(※)、朗読では無理みたい」と言ったMの台詞が印象に残りました。
(※DとMは舞台で母と息子を演じたことがあります。ちゃんと親子に見えました)
最後になりましたが、未知の役者と未知の演出家に快く朗読の許可を下さいました荻原裕幸さん、そしてご来場下さった皆様に、心よりお礼を申し上げます。
備考:荻原短歌に現れる記号の処理について
「ウッドストックの憂鬱」
この連作に登場する☆や★は、字面から鉄琴を選びました。メロディー(というほどのものではありませんが)は稽古場で適当に叩きながら決めていきました。
使用したのは、山本姉妹の実家に昔からあった鉄琴(教育楽器)です。
きらきら光るものが多いこの街では、彼のお喋りも、☆☆☆☆☆(*1)とか★★★★★(*2)なんて感じになるに違ひない。
☆☆☆☆☆(*3)/うんうんそんな言葉なら解りやすいよセールスくんも
☆☆☆☆☆(*4)/雪が降るまで屋上で待つのか?今はまだ五月だらう
★★★★★(*5)/わかつたぼくが悪かつたきみの紅茶はもうとらないよ
| *1 | 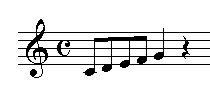 |
|---|---|
| *2 | 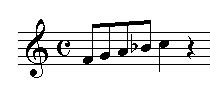 |
| *3 | 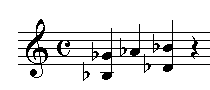 |
| *4 | 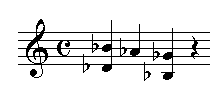 |
| *5 | 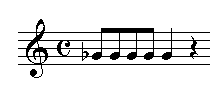 |
「ポポポポニアに御用心」
アルファベットの部分は、当初、タンバリンを叩いてみたり、色々試行錯誤を繰り返しました。しかし、どうにも声と相性が悪かったため、どうせなら全て朗読者が自力で出来るように持っていこうと、こういった形になりました。
月曜日の朝かへり来て酩酊にノブのQOQOQQOQQOQ(*6)
恋人か蛇か何かがわが前をRRRRRRPRRRPRRR(*7)
| *6 | ノブの ノブの ノブの ※デクレッシェンド(decrescendo)をかける |
|---|---|
| *7 | RuRuRu・RuRuRu・PuRuRuRu・PuRuRuRu |